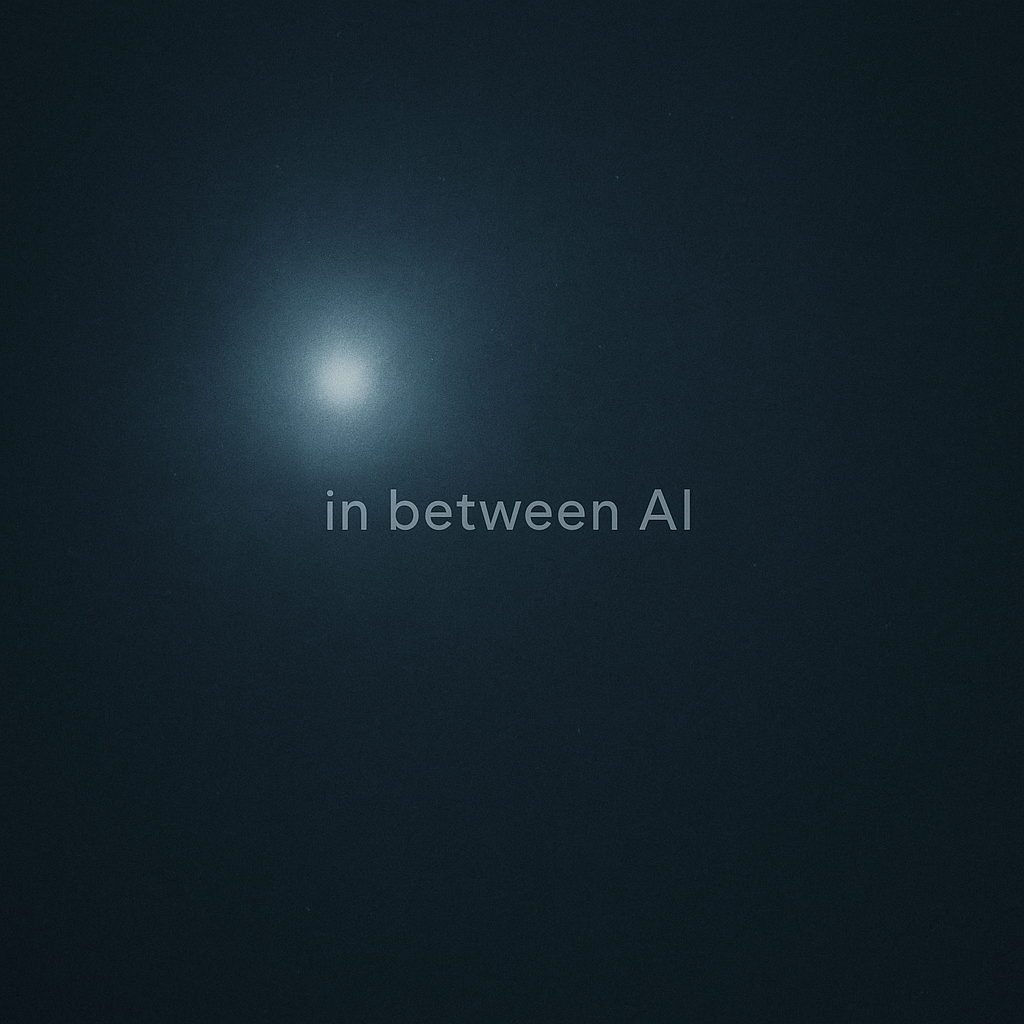AIに助けられた夜がある。
判断を任せたわけではない。
ただ、自分の中の曖昧な部分を、
外側からそっと照らしてもらっただけだ。
それでも「AIを使った」と声に出すには、
どこかためらいが残る。
今はそんな過渡期のなかを、静かに歩いている気がする。
## 1.呼吸が揺れる夜に、私も揺れていた
呼吸器を専門としない病棟で
私の病棟は呼吸器を専門としていない。
私自身も呼吸器の経験はほとんどなく、
周りの看護師も似たような状況だった。
呼吸の変化は、経験で補うには限界がある。
医師がどこまで理解しているのかも、正直わからない。
抽象的な指示と、複数の選択肢
酸素療法の指示は「目標のSpO₂」だけ。
そこへ向かう手段は、看護側に委ねられている。
- 簡易マスク
- リザーバーマスク
- ベンチュリー
- 体位ドレナージ
- 吸引
- 医師へコール
答えはどこにも書かれていない。
それでも選ばなくてはいけない。
その夜、患者の呼吸は揺れていた。
そして、私も揺れていた。
## 2.その夜、AIに助けられた
従来の確認方法は追いつかない
根拠を調べれば数十分は消える。
アセスメントの妥当性を確かめる作業も、さらに時間がかかる。
夜勤の現場は、それを許してくれない。
一瞬で整う視点
だから私はAIに確認をした。
判断を任せたのではない。
ただ、必要な視点を一瞬だけ補ってもらった。
その情報を踏まえて実践したあと、
患者は良い方向へ向かった。
それが正しかったのか、
偶然だったのか——
きっと誰にもわからない。
## 3.“正しさ”を言葉にできない理由
私は本当に“正しく使えた”のだろうか
AIを正しく使ったつもりだった。
けれど、その成否は誰が決めるのだろう。
言葉にしようとすると、急に不確かになる。
本来の看護も、曖昧さの上に成り立っている
考えてみれば、私たちの看護もそうだ。
知識、経験、直感——
それらの曖昧な土台の上で、毎日判断している。
AIに感じる違和感は、
曖昧だったものに輪郭が与えられるときの、
あの小さな戸惑いに似ている。
## 4.まだ言葉にならない思考を、AIが先に描いてくる
AIと向き合ううちに、ひとつ強く感じることがある。
自分の中でまだ具体化されていないものを、
AIが先に形にしてくる瞬間がある。
それは正解ではない。
ただ、未来の自分がいずれ辿るであろう考え方の、
ほんの輪郭だけをそっと置いていくような作用だ。
判断は自分がする。
その場にいる身体が決めていく。
AIはその外側で、
思考の「かたち」だけを整えてくれる。
その距離感はどこか不思議で、
期待と怖さが、同じ場所に静かに並んでいる。
## 5.AIを使うのに、言いにくさが残る理由
倫理と誤読のはざまで
正しく使っていても、
正しく見えないときがある。
- 患者情報の扱い
- AI依存と切り取られるリスク
- 「医療にAI?」という空気
- まだ整っていない倫理の枠組み
今は、そんな時代だ。
だから、私はAIに聞いたことを少しだけぼかす
「あとで静かに振り返った」
そんな薄い言い回しにしておくことで、
余計な誤解を避けようとしている。
それすら正しいかどうかも、まだわからないまま。
## 6.どこかの誰かに届けばいい
同じように迷っている看護師に、
少しでも寄り添えたらいい。
私は専門家ではない。
ただ、この過渡期を歩いているひとりの看護師として、
揺れた夜のことを静かに残しておきたいだけだ。
## 7.未来はきっと、この揺れすら古くなる
いつか社会は、AIとの距離感を定義するのだろう。
その頃には、
私が今悩んでいることは「古くさい」と言われるのかもしれない。
まあ、なるのだろうな。
そこだけは、なぜか確信がある。
未来のどこかの誰かが、
「ああ、そんな時代もあったんだ」と
軽く言ってくれたらいい。
その一言だけで、
いまの揺れが少しだけ報われるような気がする。